バングラの家は“誰のお金”で高くなるのか
ダッカのフラット価格を押し上げているのは、外国資本よりも“家族の仕送り”かもしれない——。そんな視点をデータで検証したのが、International Real Estate Review 掲載の論文(2016年、Vol.19, No.1, pp.98–119)です。2000・2005・2010年の全国家計調査(HIES)から計29,758世帯を取り出し、住宅価格を「送金」「住宅設備」「立地」の三つに分けて推定しました。
送金=年額の家族内仕送り(国内/海外)
ここでいう送金は、国内外で働く家族が、残っている家族へ過去12か月に送った年額。国内送金と海外送金を別々に扱い、変数は「1=1,000BDT(千タカ)」という単位で入れています。数字が小刻みに見えるのは、このスケーリングのためです。
“効き方の差”を見るための分位点回帰
分析はヘドニック価格モデル。平均だけを見るOLSに加えて、価格帯ごとの違い(安い家と高い家で係数がどう変わるか)を捉えるために分位点回帰を併用しています。これで「高価格帯の家ほど、送金の影響が強いのか?」といった問いに答えられる設計になっています。
数字で掴むコア:送金が増えると、どれくらい値が動く?
価格の真ん中付近(中央値=50%分位)では、国内送金が1,000BDT増えると住宅価格は約0.2〜0.4%上昇という推定でした。より高価な物件(おおむね上位20%=80〜90%分位)では、国内送金の影響が海外送金の2〜3倍と報告されています。
“1,000BDT”はモデル上の最小刻みです。実務で読むなら想定増分(例:10万BDT)を係数に掛けて「ざっくりこのくらい動き得る」と見る。一方で、線形に外挿しすぎると精度を失う——この前提は押さえておきたいところです。
設備・インフラは価格の“加点項目”——ただし「田舎だけ」ではない
標本の約7割が農村世帯という前提はあるものの、全国平均でも電気・上水・衛生設備の普及率は思ったほど高くありません。電気接続49%、市水道8%、コンクリート製便所11%という数字からすると、都市部でも「インフラが整った物件」はまだ限られている、という読みが妥当です。
- 電気が来ている家は一貫して高値で、価格帯が上がるほどプレミアムが大きい。
- 市水道は希少で評価が上がり、手押し井戸(tube well)は逆にマイナス寄与。
- コンクリート製便所も価格を押し上げる要素として作用。
(参考)市水道8%がもし都市側に集中しているとしても、都市世帯は全体の約3割程度。単純計算で都市内普及率は25%前後が上限——この程度の“希少さ”は残っていると見てよさそうです。
立地:ダッカへの距離は依然“決定打”
農村立地の住宅は一貫して安く評価され、ダッカからの距離が伸びるほど価格は下がる傾向が確認されています。距離係数は有意にマイナスでした。交通インフラ(MRT/BRT、幹線道路)の整備によって“体感距離”が縮めば、この評価が変わる可能性はあります。
どう使う?——投資家向け読み替え
送金は「買い手側の財布を太らせる要因」として機能し、とくに価格の高いゾーンで効き方が強い——この構造を前提に、“誰に売るか”を価格帯で切り分ける視点が必要になります。電気・上水・衛生設備のようなインフラが整っていればプレミアムを乗せやすい。逆に、整っていない物件に後付けできるなら、その分の上乗せ余地がある、と読むこともできます。
距離のペナルティは依然大きい一方、交通インフラ(MRT/BRT、幹線道路)の整備が“体感距離”を縮めるケースも出てきます。ここはニュースや政策発表とセットでチェックする部分でしょう。
なお、本稿で紹介した数字は2000〜2010年のデータに基づくもの。方向性の確認には十分ですが、実際の案件判断では最新の価格、送金額、住宅金融の状況で必ず上書きしてください。
出典:International Real Estate Review, 2016, Vol.19, No.1, pp.98–119 “Impact of Remittance Income on House Prices in Bangladesh”.

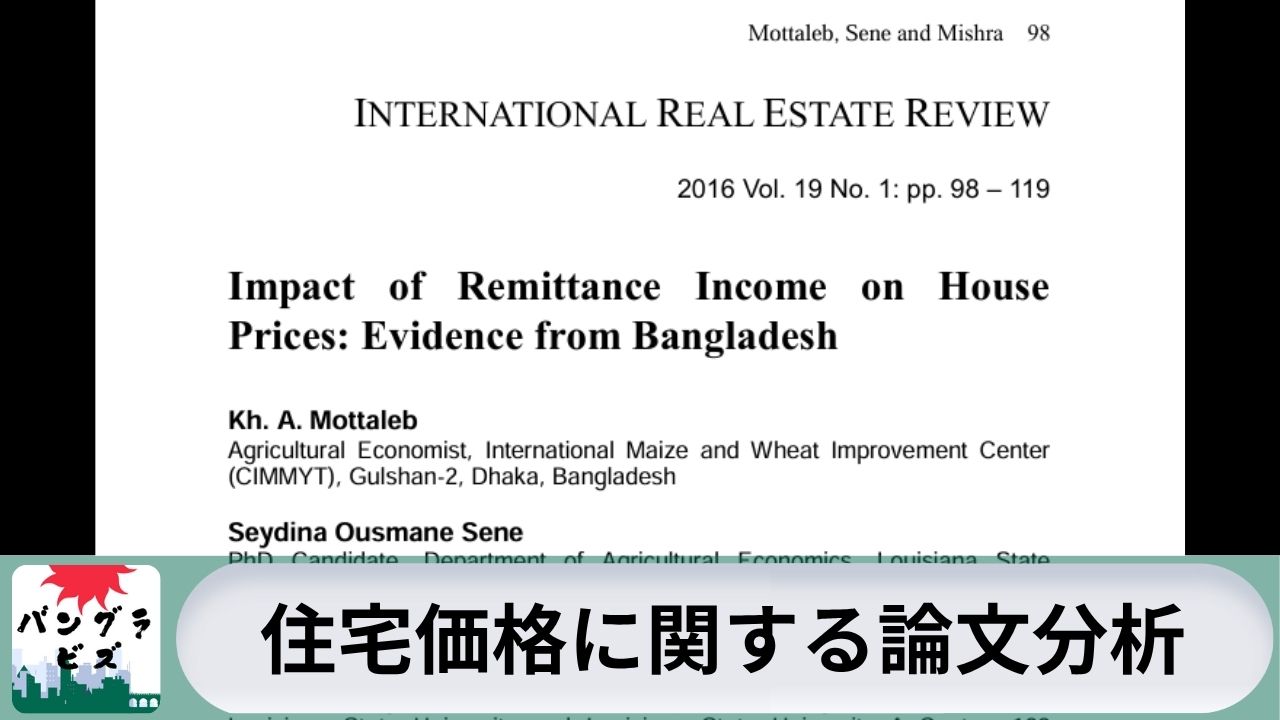

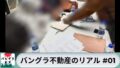
コメント