バングラデシュの不動産は、わたしたち外国人からはルールが見えにくい。
書類はベンガル語、法律はあるけれど現場では慣習が優先され、
交渉は関係性と裏合意で決まる。
この違和感に耐えられず撤退した投資家は少なくない。
しかしその裏側を理解すると、まだ誰も触れていないチャンスが眠っている市場だとも言えます。
筆者がこの10年現場で向き合ってきた事実を、連載で整理していきます。初回は「ここを外すと全部ズレる」5項目を並べます。
底堅い需要——人と金だけが増え続ける
ダッカには毎年、地方から人が流れ込む。部屋もオフィスも常に足りない。
地方から都市への人口流入は止まらず、ダッカ都市圏の人口は年々膨張しています〔1〕。結果として、住宅もオフィスも“常に不足”が平常運転。まともな管理・設備の物件は完成前から押さえられるケースが多く、プレセールやプレリーシングが普通に起きます。
土地は増えない。一方で、リミッタンス(海外送金)など“買う側の資金”は流れ続ける。
都市中心部の土地はもう増えません。にもかかわらず、海外出稼ぎからの送金や国内の遊休資金が継続的に不動産へ流れ込む〔2〕。結果として、「買いたい側」が薄くならない。完成前完売やキャッシュ買いが常に一定数あるのは、その厚みが背景にあります。
申告できない収入の“ホワイト化先”として不動産が機能している。
表に出せない収入が多い国です。所得隠しと言えばそうですが、払う側もそれを押し付けてくる構造がある。そのお金を白くする最も手っ取り早い手段の一つが不動産で、ここに資金が滞留する。キャピタルゲインが大きく、インカムゲインが弱い市場構造の裏には、こうした資金の性質もある。このテーマは後の回で掘ります。
政治リスクは“日常”として織り込まれている
デモや政変は珍しくないが、「どうせ戻る」という空気が強く、パニック売りは起きにくい。
ハルタルも政権交代も周期的に起きるが、ローカルは“一過性”として処理する。資産を投げ売りするより、様子見か、静かに買い増す行動が見られます。価格指数が急落しないのは、この“慣れ”が大きい。
暫定政権下でマネロン資金が一時冷えているが、戻る可能性は高い。
いまは暫定政権で、汚職防止委員会(ACC)が動き、不正資産を凍結・追跡中。これが有力者が“表に出づらい資金”を委縮させ、投機的売買は一時的に冷え、買い控えによる多少の値下がりが見える。ただ、この状態は長期化しないと見る人が多い。悪いことしてない側にとっては、むしろ今が買い時、という見方も現場にはあります。
“カオス”の正体はローカルの合理性
契約書で安心を取りたい外国人と、人間関係で担保するローカルの文化がズレる。
外国人は条文と証跡で安全を確保しようとしますが、現地では「この人が間に入っているなら大丈夫」という信頼の連鎖で動く。だからプロセスの順番が違う。先に腹を合わせ、紙はあとで付いてくる。このズレを理解せずに交渉に臨むと、スタート地点から噛み合わない。
このズレの解消にこだわるあまり、高値掴みや書類トラブルがおきて足をすくわれる。
ベンガル語書類の読み違い、権利関係の二重化はもとより、“外国人価格”の設定にいたるまで、カモにされてしまう典型的なトラブルはここから生まれます。次回「落とし穴編」で詳しく説明します。
逆に、仕組みを把握できれば無駄なリスクはかなり削れる。
契約書外の“了解事項”をどう把握し、どう記録に残すか。誰に確認し、どこで線を引くか。ローカルの合理性を理解した上で、自分の合理性を崩さないこと——それで大半の無駄な損失は避けられます。
株式市場と不動産価格の“ゆるい連動”
上場デベロッパーの資金状況と株価の温度感が、開発スピードと販売条件に反映される。
DSEの不動産関連銘柄の資金調達環境が良い時期には、土地取得・広告・販売が前のめりに進む。逆に苦しい時期は販売条件が変わる。統計的な強相関までは言いませんが、“ゆるく連動”しているのは現場では普通に見える現象です。
不動産単体で見ず、市場の裏側(金の出処と温度)を見る。
誰の金が、どれくらい熱く(資金が積極的に投下されてる、リスク許容も高い)、あるいは冷えて(様子見、資金が出にくい、条件が厳しい)動いているかを押さえておくと、相手の譲歩ラインやスケジュール変更の余地が読める。土地と建物だけを追っていると判断が遅れる。
現場で積み上げた視点(筆者の立場から)
誰にでも参入を勧めるのは無理。判断材料は開示する。
この市場は、誰にでも「やりましょう」と言える場所ではない。ただ、判断材料はできるだけ見せたい。読んで「やめる」も正しい判断。
小口で資金を集めるスキームは、投資の実態が追えなくなる。
複数から小口で集めるファンド的スキームや、区分所有に似た持分販売は増えているが、資金の流れや実際の土地権利が最後まで追い切れないことが多い。情報の非対称性が大きすぎ(投資家に届く情報が切り取られすぎ)て、判断材料は常に限定的になる。こういう設計は「任せておけて楽」だが、慎重に。
逆に“一人で買い切れる”形を取れるなら、激アツ。
一つの土地、物件を単独で押さえられる規模なら、コントロールが利く。権利関係も資金の流れも自分で握れる(確認できる)ので、勝ち筋が一気に増える。ここに入れるプレイヤーは少ない分、余白は大きい。
“投資家のガードを固める第三者”として立つ。
裏ルールは知るが操らない。線を越えない。ローカルの合理性を理解しつつ、「金の出入口」「権利の線引き」「あとで説明できる証跡」、これらは自分で握る。この視点から、具体的な手順・注意点を今後の回で落としていきます。
次回予告
【連載】バングラデシュ不動産のリアル #02|落とし穴編:外国人が踏む5つの穴
書類/法律と慣行のズレ/外国人価格/資金の“蒸発”ポイント/関係者マネジメントの失敗例…ここを先に潰しておけば、最初の事故は回避できる。
脚注(参考)
〔1〕Dhaka Population 2025, World Population Review(2025年時点:約2,465万人、前年比約3%増)
https://worldpopulationreview.com/cities/bangladesh/dhaka
〔2〕Bangladesh Bank “Worker’s Remittance” データ(2025年5月:約2.97億ドル、単月で過去2番目)/The Business Standard
https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/wageremitance
https://www.tbsnews.net/economy/banking/bangladesh-receives-297-billion-remittances-may-1157191

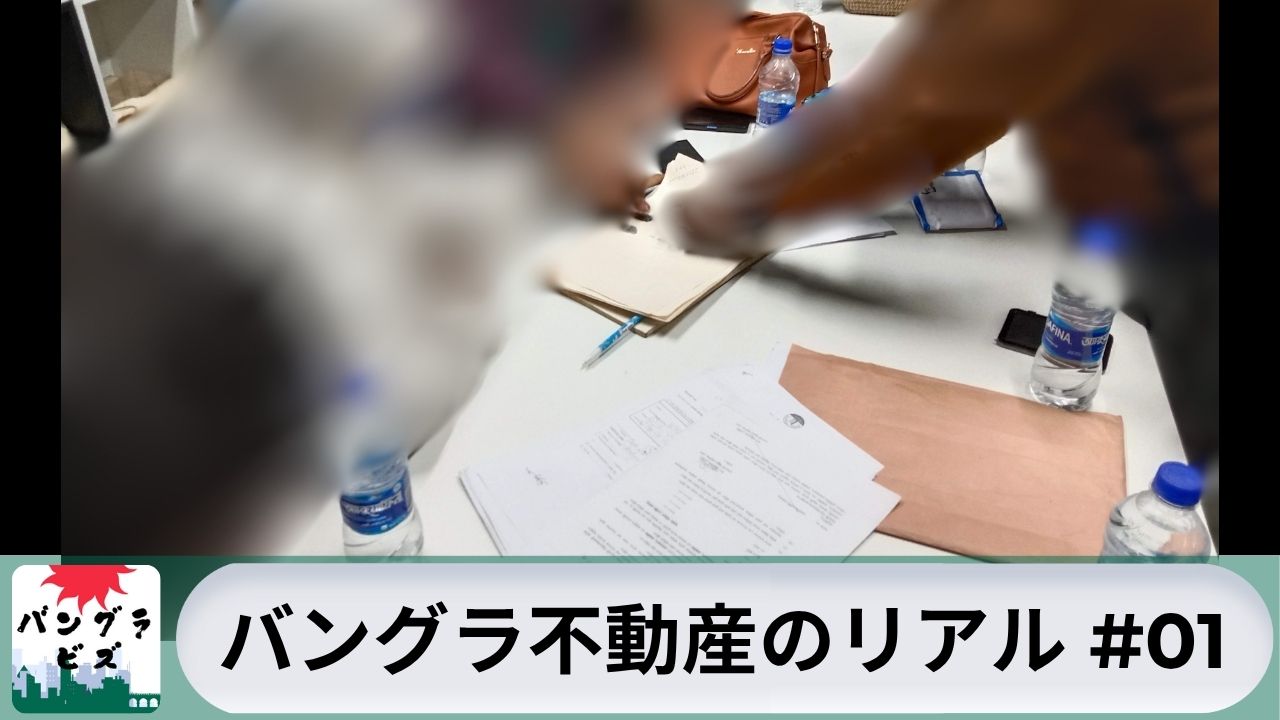


コメント